-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
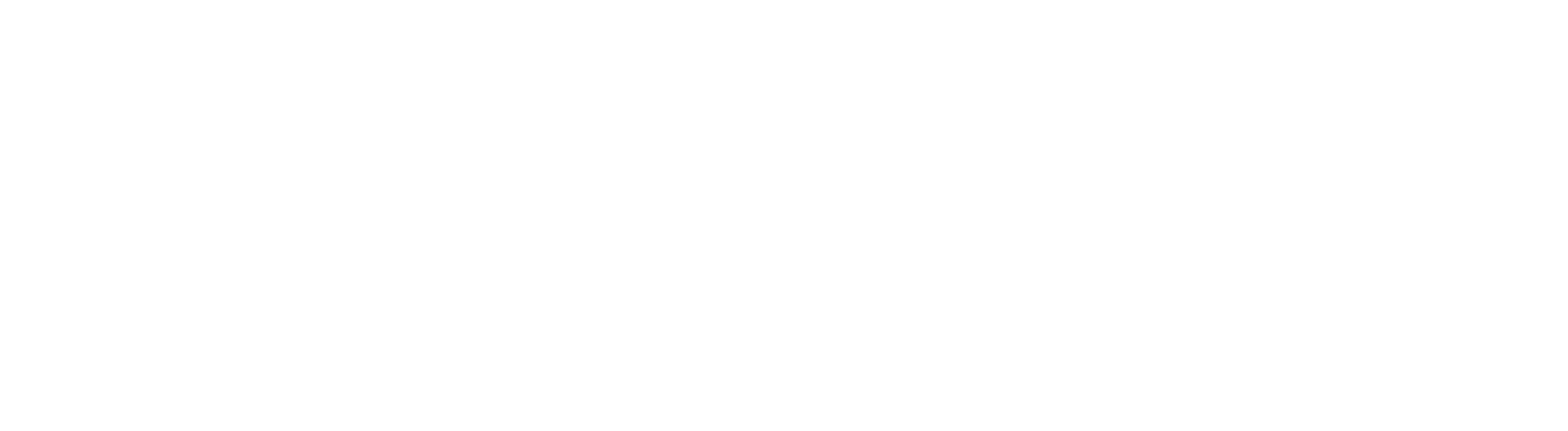
皆さんこんにちは!
株式会社松場防災設備、更新担当の中西です。
~リスク別設備選び~
厨房の油火災、工場の粉塵・溶剤、充電設備のリチウムイオン電池——“燃えやすい現場”には、一般ビルと違う対策が必要です。ここではリスクに合わせた設備選びと、**DX(デジタル点検)**までを、実務で使える粒度で解説します。⚙️
厨房(揚げ物・グリドル):油過熱・グリス堆積・ダクト内着火
溶剤・塗装ブース:引火性蒸気・静電気・換気不良
️ 粉塵(製粉・木工):浮遊粉塵の爆発・堆積粉塵の二次爆発
蓄電・充電エリア(Li-ion):熱暴走・再燃リスク
溶接・切断:火花・スパッタの周囲可燃物着火
調理油用自動消火装置(フード/ダクト/レンジ連動)
→ ふた・薬剤・ガス遮断が同時に働く設計が安心
グリスフィルタ清掃&ダクト定期洗浄
ガス遮断・非常停止ボタンの“見える化”
熱・煙感知の最適化:蒸気が出るゾーンは熱感知中心に
実例:フード内自動消火+ガス遮断で、深夜の油過熱を自動鎮圧。復旧は開店前に完了。
泡消火設備:可燃性液体に強い(貯槽/受け皿のサイズに合わせる)
不活性ガス消火(窒素/アルゴン系):人員在室の安全を考慮し、警報→退避→放出の手順を徹底
防爆型機器&アース/静電対策:着火源を作らない
熱・炎感知の併用:高粉塵や蒸気で煙感知が不利な現場に
局所排気+ダクト内火花検知→スパーク消火
掃除=防火:堆積粉塵は発火→二次爆発の燃料
粉塵対応感知器(加熱式/炎感知)を選定し、位置と高さを設計
早期検知:温度/ガス(VOC/CO)センサの多点配置
冷却・隔離:金属バットや耐火ボックス、水冷却での延焼遅延
充電管理:過充電防止、隙間確保、保管温度の管理
大量保管・大容量設備は必ず所轄消防へ事前相談
一度暴走すると再燃が起きやすいのが特徴。初期消火+冷却+監視の三段構えが鍵です。
クラウド台帳:QRで設備・履歴・写真を紐づけ
遠隔アラート:受信機警報をSMS/アプリで即時共有
点検アプリ:チェックリスト自動生成、是正依頼をワンボタン
データKPI:誤報率・復旧時間・交換周期をダッシュボードで可視化
現状調査:火気・油・粉塵・溶剤・充電の有無、換気量
法令ヒアリング:用途・規模に応じ所轄消防と事前相談
基本設計:感知方式・消火方式・電源・遮断連動
施工計画:休業・夜間・エリア分割など操業影響を最小化
試験/検査:連動・遮断・放出・復帰の一連シナリオを実機で
教育/訓練:初期消火・避難・再開手順を動画+現場訓練で浸透
運用:DX台帳で点検→是正→更新を回す
Q:粉塵が多くてよく誤報します…
**A:**感知種別の見直し(熱/炎)+感知器高さ変更、ダクト負圧でゾーン分けを。
Q:夜間の無人厨房が不安…
A:フード自動消火+ガス遮断+遠隔アラートの“三点セット”で検知→遮断→通知を自動化。
Q:充電ラックを増やしたい
**A:**ラック間隔・温度監視・ケーブル容量を再設計。大量設置は事前協議が安全。
熱源の自動遮断ボタン位置
フード/ダクトの清掃周期
感知器の種類・高さ・距離
消火器の薬剤種別(油/電気/金属)
電源・ガス遮断の連動
泡/ガス放出時の退避ルール
防爆型器具/アースの整備
局所排気の風量・フィルタ️
粉塵の堆積管理
Li-ion温度/ガス監視
充電エリアの空間確保
避難経路・誘導灯
非常電源の負荷試験
訓練(年2回目安)
DX台帳の更新率
“燃えやすい現場”は、設備の“組み合わせ”が命。
厨房は自動消火+遮断+清掃、工場は消火方式+防爆+排気、充電エリアは監視+冷却+隔離で立体防御を。
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社松場防災設備、更新担当の中西です。
~通る・止めない・ムダを作らない~
消防設備は“設置して終わり”ではありません。法令適合(通る)、故障ゼロ(止めない)、**コスト最適(ムダを作らない)**を同時に満たしてこそ、建物の価値は上がります。本稿は、管理者・オーナー・施設担当向けに、点検から改善、KPI設計までを実務目線でまとめた保存版です。
自動火災報知設備(自火報):感知→受信→警報
スプリンクラー / 水噴霧 / 泡:自動的に放水し初期消火
消火器:粉末/強化液/二酸化炭素など用途で使い分け
屋内/屋外消火栓・連結送水管:消防隊の放水インフラ
誘導灯・非常照明:避難経路の“見える化”
️ 排煙設備:煙を抜き視程を確保
非常放送・非常用電話:情報を正しく届かせる
非常電源(非常用発電機・蓄電池):停電時の命綱
防火戸・防火シャッター:延焼を区切る“建築側の装置”
どれか一つでも機能不全だと“全体の安全度”が下がるのが消防設備の特徴です。
一般に機器点検(おおむね6か月ごと)と総合点検(おおむね年1回)の二層で運用するのが標準です。
ただし建物用途・規模によって報告頻度が異なるので、所轄の消防へ事前確認を。
点検の基本フロー
事前計画(エリア・停電/断水手順・代替警備)
作動試験(受信機・感知器・音響・表示灯)
放水/加圧試験(必要に応じて減殺措置)
誘導灯・非常照明の照度・点灯確認
設備台帳・是正票の更新 → 是正工事 → 報告
法令/条例の確認:用途変更・増改築・テナント入替時は要注意
図面の最新化:平面・系統・配線・バルブ系統をクラウド保管
台帳の標準化:QRで設備個体を紐づけ、交換履歴と写真を一元管理
是正の優先度付け:A(危険・重大)/B(要計画)/C(改善)で即断
MTTR(平均復旧時間)
故障件数/100台(感知器・誘導灯・発信機など品目別)
点検実施率/是正完了率
誤報発生率(誤作動要因を除去)
水圧・放水量・電池容量の健全率
KPIは月次レビュー+年次の更新計画(更改・増設)に直結させましょう。
消耗品の先回り更改(誘導灯バッテリー・感知器の経年)
共通部材の在庫化(予備機・弁パッキン・表示灯)
複数設備の同時停電/断水で一括試験=工数圧縮
誤報の原因学習(熱源・蒸気・粉塵・害虫)→ 感知器種類の見直し
ホテル:誤報月3件 → 0.3件に
厨房周辺の煙感知→熱感知へ変更、換気連動強化
誘導灯1系統に予防的バッテリー交換
誤報要因を毎回ログ化→ 3か月で誤報90%減
受信機:ランプ・表示・履歴
感知器:汚れ・作動・設置環境
発信機:押しやすさ・復帰
音響・放送:全域で可聴
誘導灯:点灯・バッテリー・破損
消火器:圧ゲージ・腐食・有効期限
消火栓:ホース・ノズル・水圧
連結送水口:キャップ・ゴミ・パッキン
排煙:作動・復帰・障害物️
非常電源:始動・負荷運転・燃料/蓄電
**“通る・止めない・ムダを作らない”**は、
**計画(法令)→ 点検(KPI)→ 是正(優先度)**のループで実現できます。
![]()